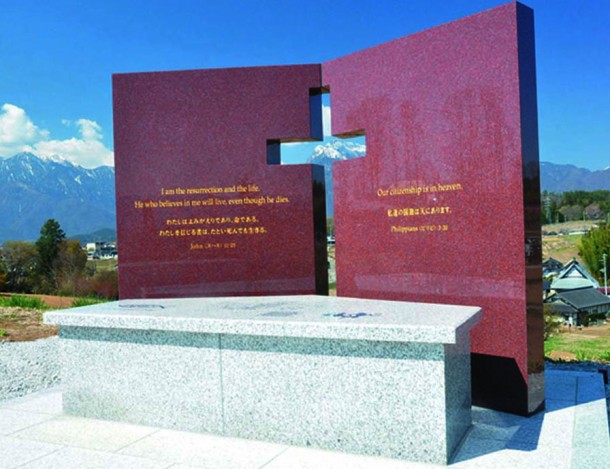五輪塔の正しい施工例
仏様そのものを表す、ありがたい形の五輪塔。現在の和型墓石はこの五輪塔が簡略化した形と言われています。
ところが、五輪塔を建てる際、まちがった建て方をしている例があまりにも多い・・・!当店ではせっかくのありがたい五輪塔を正しく建てていただけるよう、アドバイスしています。(詳しくはこちらをご覧ください)

今回ご依頼いただいたS家には、もともと古いご先祖の代々墓がありました。
最近、両隣のお宅が新しい墓石を建てたので、うちも新しくしよう、とお考えに。
ところが、お隣2軒はどちらも古い代々墓を残したまま新しい代々墓を並べて建てています。新旧の”○○家之墓”が2つ並んでいるのです。
S家でも、「納骨堂を新設するにあたり、お石塔が古いので新しい石塔にしたい。でも、敷地もあるし、もったいないし、古い墓石も残したい。」というご相談でした。
しかし、伊藤石材は不要もの、誤った形式は薦めません。代々墓が2基並んでいるということは、家庭で言ったらお仏壇が2つ並んでいるのと同じなのです。
「1つの家で本尊を2基も並べて建てるのは変ですよ。同じものですよ。どちらを拝むんですか?ご本尊を新しくするのなら、古いものは片づけましょう。そうでなければ、五輪塔という仏塔を建てる祀り方がありますよ。」ということで、角柱墓は残しつつ五輪塔を増設、で話はまとまりました。
そもそも、古い墓石は、今では手に入らない国産山崎石を使った、スリン座のついた立派なもの。再研磨をかけて再生し、同系色の新規五輪塔を建てることで、仏式としては理想的なお墓になりました。

中央が、古いスリン座のついた墓石

中央にお墓、左に墓誌、右に五輪塔。手前に並ぶ古いお石塔も洗浄してきれいになりました。

後ろの様子。外柵石材は磨き加工とザラザラの”びしゃん”のコントラストで仕上げました。