タイマグラばあちゃん
北杜市で『タイマグラばあちゃん』の上映会があります。
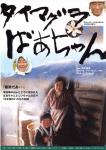
「タイマグラ」とよばれる岩手県早池峰山のふもと、水も電気もつい最近までない人里はなれた山奥で、自給自足しなから一人暮らしをしてきた向田マサヨさんの晩年を描いたドキュメンタリー映画です。
私はまだ見てませんし、この上映会も日程が合わず行けません。
だから以下の内容説明は単なる憶測です。
ばあちゃんは、ジャンヌ=ダルクのように国家を救ったとか、キュリー夫人のように大発見をしたとか、マザーテレサのように貧しい人に献身したとか、そんな偉業を成したわけではありません。
普通に、四季のうつろいのなかで、生活し続ける、それだけです。
それは変化と刺激に富んだ現代社会で暮らす私たちにとって、あまりにも平凡で退屈、かつ不便な生活のように見えます。
「ただ、生きる」
小泉堯史監督の『阿弥陀堂だより』は見ました。
淡々と、信州の雪深い山村・飯山での生活が描かれる中、樋口可南子演じる<妻>の「パニック障害」という病気と、彼女が都会の病院勤務に少しだけもどる期間があり、それが逆にこの映画にフィクションとしての客観性を持たせ、主人公夫婦の田舎暮らしがどっか別の世界ではないことを感じさせる重要なエッセンスになっていました。
映画の中で、お盆の送り火を見つめながら妻が「私たちも先祖になっていくのかしらね」というセリフが私は一番好きです。
この二つの映画が、別に不便な生活をしろとか、自給自足して暮らせ、などということを言ってるわけではないでしょう。
もっと根本的に、「ただ、生きる」ということを、考えるでもなく感じていけばいいんだと思います。
今の生活を変える必要もなければ、悟りをひらくものでもない。
きっと上映会場を出たとき、甲斐駒がひときわきれいに見えれば、それでOKなんだと思います。
そういう思い、したくないですか?
上映会案内は以下のとおり。
日程:2月17日(土) 13:30開場 14:00開演
会場:高根ふれあい交流ホール(北杜市高根総合支所西側)
料金;前売1000円 当日1200円
こんなサイトも見つけました。
タイマグラって?
http://www.taimagura.com/



