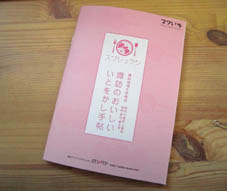ナチュラルハンドケアオイル
手作りハーブオイルのハンドクリームづくりを教えてもらいました。
「杜の子育てネットワーク」が主催する「ナチュラルハンドケアワークショップ」。
森のようちえんピッコロのママさんたちが集まって、「森のナース」ふしみまあやさんが講師。
自分や子どもの体のことをちゃんとわかって、どこが悪いか、どうすれば直るか、を考えられる人になろう、というコンセプトです。
ピッコロではケガや虫さされ、動物に襲われる、などの危険と隣り合わせ。
蜂やクマの習性もきちんと子どもたちと共有し、自分の身を未然に守る、それでも被害にあったときの応急処置や病院搬送のしかたなど、すごくよく勉強します。
また、アレルギーなどの持病も、なるべく薬に安易に頼らず、根本的な生活方法を模索したり、自然のケアをしたり、と考えるお母さんが多いです。
ナチュラルハンドケアはハーブを浸したオリーブオイルとミツロウを使った、手作りのマッサージオイル。
作る前にまあやさんはこんな風に話してくれました。
「ハーブとか使って、すごく自然、と思うかもしれないけど、自然のものだからこそ強すぎて肌に合わない場合もあります。ナチュラル=いい、と決めつけず、自分の体を知って、感覚や直感をたいせつに、勉強しながら使っていきましょう」
確かに、薬だって元は自然界から成分を抽出したもの。
専門家が実験や考察を繰り返して作り上げた。
純粋に、ある効用だけをとって薬にしたものと、他にもいろんな成分が混じっている天然のものとでは、効能は違ってくる。
つまり自然のものは無駄やリスクも増える。
そういえばまちこぶ味噌作りのときに講師のオオタさんも言ってました。
「天然酵母がいいイメージで、イーストは普通以下のイメージみたいに言われてますが、
イーストも酵母の一種。」
前置きが長くなりました。
ワークショップの場所は小淵沢・蔵やグリーンズ。
自然食品やフェアトレードの食品・衣類などを販売、豆腐づくしのランチをいただけたり、エスニック系のライブが行われたりする、ちょっとマニアックな集いのお店です。



ワークショップではまあやさんがストックしているハーブオイルを分けてもらいます。

庭に生えているハーブ3種(ラベンダー、ローズマリー、カレンデュラ&ワイルドパンジー)
をそれぞれちょっとイイ食用のオリーブオイルに漬け込み、ハーブオイルを作ります。
そのままパスタなんかにも使えるもの。
エッセンスオイルを使う場合もありますが、「エッセンス」だけに、成分が強すぎると感じる人もいるので、今回は生のハーブを漬け込んだオイルを使います。
小瓶にミツロウとオイルをいれ、湯せんで溶かします。

完全に溶けたら火からおろし、固まるまでひたすら混ぜます。
混ぜないとミツロウとハーブオイルの成分が分離してしまうのです。
使う家族のことを考えながら愛情こめて混ぜるのがポイント♪

完全に固まったらできあがり。

超カンタン。だれでもできる。Mooでもできそう。
ミツロウチップは小瓶の1/4程度使いました。
固いのが好きな場合はミツロウを多くし、逆に全身にマッサージオイルとして使いたい場合などは少なくしてゆるくします。
私はあまり聞いたことのない、カレンデュラ&ワイルドパンジーのオイルを分けてもらいました。
オイルを嗅いだときはかなり強烈な薬草のにおいがしたのですが、
ミツロウとまぜた完成品を手にぬってみると、優しいイグサのにおい。
畳の部屋にいるような和風な感覚です。
自分で作ることの一番のメリットはコストパフォーマンス。
いいオイルだと軽く1000円くらいはしますが、今回は講習料も含めて500円。
もちろん100均やドラッグストアで安く売ってるハンドクリームもありますが、そこはなんとなくロハスにちょっとこだわってみたいもの。
ミツロウも余分に安くわけてもらったので、自宅のハーブをつけこんで、また作ってみようと思いました。
これで寒い時期の手あれも改善するかな。
なにせ、つけてそのままお料理したりできるのがいい。
ただし、乳児には念のためハーブは使わず、キャリアオイル(ハーブをいれないオリーブオイルやホホバオイルなど)のみのほうがいいとのことでした。