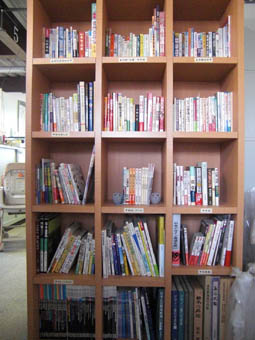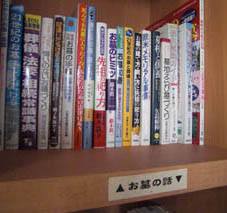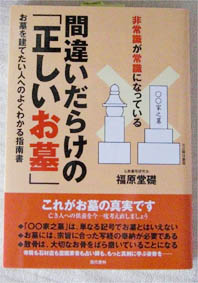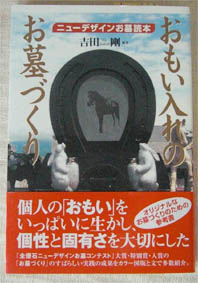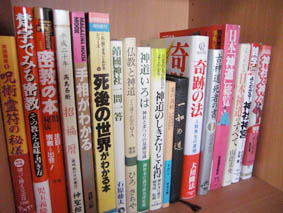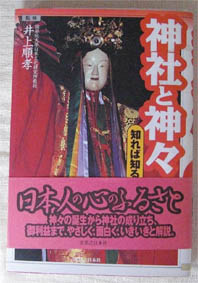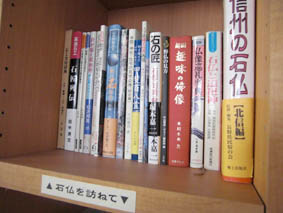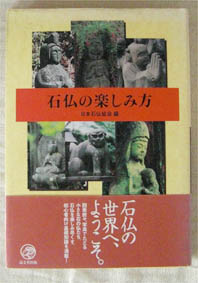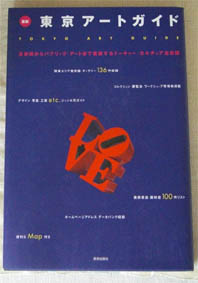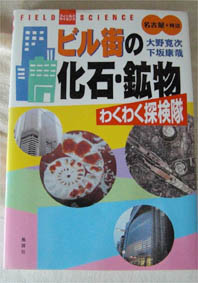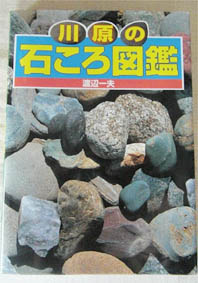家族葬について
NHKのあさイチ、今日のテーマは「家族葬」でした。
家族やごく身近な知り合いだけで、故人をじっくりと送ることをめざす「家族葬」。
6割の人が希望するというこの葬送の形を、メリットデメリットをふまえて紹介するという内容でした。
誰もが迎える「死」。たいていの場合、一度は親しい人を「送る側」になることについて、きちんと考えてみることは重要なことです。
ただ、いつもこの手の番組は、ハラハラしながら見ているのが本音。
「心をこめる」という殺し文句の陰に、安易に「安さ」「簡便さ」「人間関係の希薄さ」を助長するような内容にならないかどうか。
もちろん、どんな番組でも、とりわけNHKですから、望む人が多い反面の問題点の指摘も忘れてはないのですが、
興味をもって見てる人ははなからこのテーマに共感するから見るのであって、自分の考えを曲げるつもりはあんまりないのではないでしょうか。
よっぽどデメリット部分を強調しすぎるくらいにしないと、危機感は伝わらない。
ゲストの一人が山口もえちゃんではちょっと弱い・・・。
ですから、今日はあえて、丸ごとは共感できない立場からのツッコミを。
(どうも、NHKモニターの癖が抜けないなぁ)
まずタイトルが危険。『格安で実現!私らしいお葬式』。
このタイトルで、まず葬儀屋に多額の金を払うのはバカバカシイという印象を植え付けてしまう。
金をかければいいってもんじゃないけど、かけないからいいもんでもないだろう。
「従来のお葬式」とは決して、葬儀屋に一切をまかせて自分は何も希望を言えない、というものではない。
本来、従来のお葬式とは、近所や檀家同士など、地域社会の中で行ってきたもの。
番組中でも紹介されている、「3日間戦争」と言われる雑務の煩雑さを、当家がするのはそもそも無理。
喪主はムードメーカーとしてその場にいるだけ、あとは葬儀委員長に任命された組内の会長さんなどがすべてを仕切る。
これは田舎ならまだ残っている風習ですが、都会ではそんなメンドウなことは皆無になり、結果葬儀屋が代行して行うというパターンが一般的になりつつある。
(田舎ですら、近年組内だけで葬儀をあげることは少なくなっています)
番組ではドラマ仕立てで家族葬の一例を紹介。このドラマがまた、センチメンタルなまでに主人公である喪主(故人の妻)に感情移入させる内容になっている。
祭壇、花は菊、戒名、お経…
ふだん馴染みのないものだから、お葬式だけそういうものに触れるのは抵抗がある、
「(葬儀屋)仏様は北枕が普通」←→「夫はいつもこちらを枕にしていましたから」と断る妻。
「お坊さんの手配を…」←→「意味もよくわからない、聞きなれないお経をあげてもらっても夫らしくない。戒名もいらない」
宗教の自由を約束された国家だから、どういうスタイルにしようともちろん自由。
でも、人間が精神と知恵を結集して培ってきた宗教観を、現代の「自由」という名の下の「無知」で片付けてしまってはあまりにもったいない。
お経や仏事の意味を少しでも知ろうとしたことがあれば、こんな言葉は出ないはず。
葬儀屋は専門家だけあって、仏事神事、風習慣習、道徳常識はよく勉強している。
この機会にそういうものに触れてみよう、勉強してみよう、というのも自分の身になるのに。
「親しい人だけで送る」
これ、実はある意味すごく排他的。
だいたい、「親しい人」をどの線で区切るつもりなのか。
普段会話している人と親族だけ(親族も何等親まで?)では、逆に今の社会に合わない。
おさななじみや昔の同僚、年賀状だけのつきあい…仕事や結婚の活動範囲が広くなって、ふだんつきあえないけどその故人をしのびたい人は多いはず。
私はまだ親しい人を送る機会が少ない年代だから、ちょっと顔見知り、あまり会えないけど懐かしい、尊敬している、というようなたぐいの人が多い。
その別れの場に行く機会を設けてもらえないのはかなりさびしい。(ある意味、失礼)
「家族葬」「密葬」の名のもとに、「来るな」と断られているようで。
ただ、これにはいい面もあることはあって、亡くなった直後の遺族のつらい顔を見るより、半年くらいして落ち着いてからのほうがこちらの気持ちも楽だったりする。
平服で訪問し、ゆっくり思い出話をできる場合もあるから。
少人数葬儀を選んだ家は、そういう風にバラバラと訪問客を受け入れるのをヨシとする覚悟くらいはもつべきだろう。
困るのは遠方の場合や、個人的にわざわざ訪問するほどの仲でもなかった場合。
お葬式で集まった者同士、しんみり話をすることも、大事にしたかったりするから。
葬儀は、冠婚葬祭の中でも最も短時間にやるべきことが山積みになる儀式。
大勢の人員総動員してやっと成し遂げられる総合事業なのだ。
地域社会のつながりが希薄になったことで生じた問題を、解決するのはお金や簡素化ではない。
極論。
ただでさえあわただしい葬儀で、ムリヤリ個性を出さなくたって、
あとでいくらでもその人らしい偲び方、残された者同士の心の交流はできると思う。
それでも葬儀という儀式はやっぱり必要。それは故人や遺族のためだけでなく、人生で彼らに関わったすべての人に対する礼儀として。
その上で、「その人らしさ」が出せればもちろん理想的。
こういう番組を流すことが、そもそもの問題である「つながりの崩壊」を黙認することにならなければよいが。