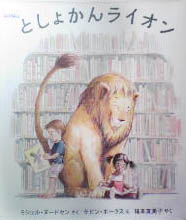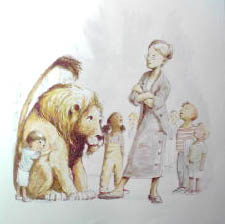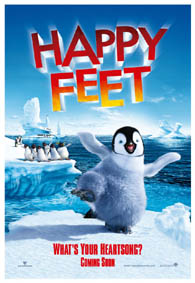金色の野
武川町・柳澤集落の地名の由来ともなった、柳澤氏の屋敷跡と思われる場所に建つ観音像。


釜無川右岸の平野は山梨県でも有数の米どころ。
武田氏初期の頃から「武川米」と呼ばれて高く評価されていました。
昭和天皇の献上米に指定されていたことも。
武川米の田んぼ一帯が「北杜24景」に指定されたので、取材かたがた、あらためて撮影に行ってきました。
今はまさに実りの時期。
秋晴れが2日続き、久しぶりに山が全部見える、最高に絵になる日。
黄金色の田が広がって、その向こうに勇壮な南アルプスの姿が見えます。




農家のおばさんの姿がとても美しいです。
モデルになってもらって、いろいろお話させていただきました。
穂先の茎が白くなってきたら刈り取り時期。
今日はあと数日に迫った刈り取りの直前の、スズメよけのロープをはずす作業をされていました。
いよいよなんですね。


せっかくなのでウチの娘も近くの田んぼへお散歩。


その者青き衣をまといて 金色の野に降り立つべし
すみません。最近親子で「ナウシカ」にハマってるもので・・・