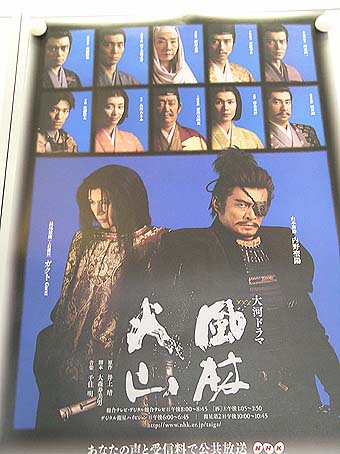にわか鉄道ファン
この夏、私はにわか鉄道ファンになりました。
正確にいうと鉄道写真ファンです。
鉄道はもともと好きで、マイレージよりVIEWCARDポイントためてグリーン席や新潟の地酒もらうほうがうれしいし、時刻表も一時期は毎月買っていました。
今回おこがましくも仲間入りさせていただいたのは、鉄道写真撮影です。
発端は小海線・ハイブリッド車両。
先月、営業車両として世界初の、ディーゼルと蓄電池による省エネ車両が小海線で始動。
このニュースを勤め先で発行する情報誌の記事にしようと、取材のため小海線の写真を集めることにしたというわけです。
小海線は鉄道ファン、写真ファンの間で根強い人気。
雄大な山景色と広大な田園を背景に、たった2両のディーゼル車(頭に電線がないからすっきりした姿)が走る風景はまことに絵になります。
でもなんとなくオタクっぽくない?と、休日になるとわらわらと集まってくるカメラマンたちを横目で見過ごしていました。
ごめんなさい。私が間違っていました。
こんなにロマンあふれるシュミを持つ皆さんを尊敬します。
写真は毎月仕事でたくさん撮っているとはいえ、カメラの使い方は素人。
こんな私でもそこそこの絵になってしまうのですから、やっぱり小海線はステキです。

 南アルプスをバックにしたハイブリッド車両「こうみ」
南アルプスをバックにしたハイブリッド車両「こうみ」
今回のお目当てはもちろんハイブリッド車両。
営業開始したといっても全ての線で切り替わったわけではなく、まだ小淵沢発は日に4本です。
朝10時01分。小諸始発の便が小淵沢駅に到着し、すぐ折り返し運転で10時07分に再び野辺山へ向けて出発します。
というわけで10時少し前にある地点で列車がくるのを待機。
上下線あわせて2回のチャンスにかけます。
そのある地点とは、通称「小淵沢の大カーブ」と呼ばれるところ。
実は小海線は小淵沢ではなく、中央本線の西隣の駅・信濃境から発着させる計画だったのを、なんらかの政治的な理由かどうか、急遽小淵沢に変更したという噂があります。
それで、途中まで作っていた線路を小淵沢駅につなげるため、岩久保区のあたりで大きく方向転換したのが現在の形だとか。
そんないきさつの是非はともかく、小淵沢駅から次駅甲斐小泉駅への車窓は実にドラマチックです。居ながらにしてまるでメリーゴーランドのように南アルプス〜八ケ岳をぐるーっと見渡す動画。
今年はそれに加え、水田に大きな稲文字『風林火山』を見ることができます。地元の小学生によって、字の部分だけ穂の色が紫になる別の品種の稲が植えられました。

この稲文字とハイブリッド車両と山の景色を一枚におさめたいと田園を駆け抜け、やっとそれなりのスポットを見つけて列車を待ちました。
天気はまあまあ。雲は多いがかえって夏らしい雰囲気をかもし出し、山の稜線も見えます。
動かざる山の景色に疾きこと風のごとく走り去る列車。
スポットを探す過程と、この一瞬がいいんだろうなぁ。鉄道写真って。
実際に乗り心地も体験してみました。
休日、娘と野辺山まで往復します。
やはり音が少ないかんじ。車椅子でも大丈夫なように入口は低く広くとってあるのも好感がもてます。
窓からは例の稲文字がますますよく見えます。
小淵沢インターのそばを通り過ぎ、森をいくつも抜けて4つめが清里駅。その先はJR最高地点(標高1375m)があり、高原レタス畑の中を抜けて野辺山駅に到着です。
駅舎が「銀河鉄道の夜」のサザンクロス駅を思い出させる、ノスタルジックかつファンタジックなもの。


娘は列車に乗れるだけでむやみにはしゃぐ。
いさめながらも私もわくわく。
大人も子供も幸せになれる、大きな夢をいっぱい乗せた、鉄道の旅。
 ハイブリッド車両と従来の車両(風林火山デザイン)
ハイブリッド車両と従来の車両(風林火山デザイン)
 ここから出発、小淵沢駅
ここから出発、小淵沢駅