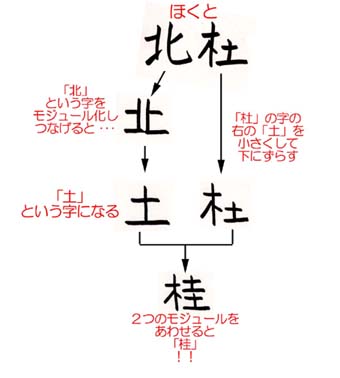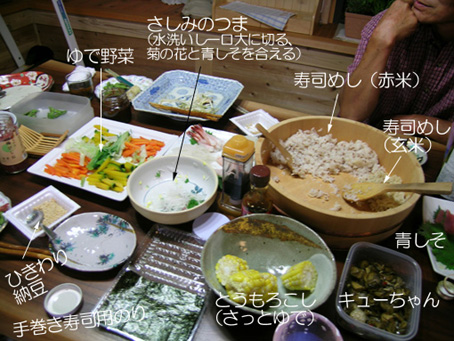鉄と石の組み合わせアイテム
鉄造形作家の上野玄起さんのご協力により、こんなアイテムができました。
帰ってくるのが楽しくなる、玄関周りのアイテムです。
かさたて
ト音記号のような形の鉄細工の下に、お豆のように真ん中がへこんだ石の受け皿。
スリムですが5〜6本は楽に入ります。
石:グレー御影石 本磨き加工。
参考上代:30,000円

 ←クリックで画像大きく
←クリックで画像大きく
スリッパラック
木の枝が上にのびているような形の鉄細工の下に、シンプルな円形の石台。たくさんの握りこぶしが「がんばるぞ、がんばるぞ」と言っているようにも見えませんか?
石:薄赤色御影石 本磨き加工
参考上代:30,000円

 ←クリックで画像大きく
←クリックで画像大きく
手洗い
ガラスボウルはクラフト葉音さん作。
緩やかなカーブをつけた波型?の石天板に沿った形のタオルハンガーを鉄で。
石:薄黄色大理石 本磨き加工
参考上代:1セット40,000円 ※取り付け、水道設備工事別途

 ←クリックで画像大きく
←クリックで画像大きく