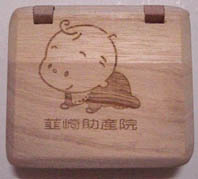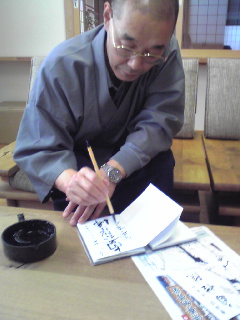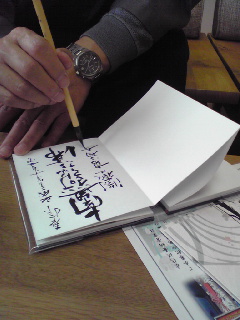へその緒信仰
Kuhのおへそがとれました。
この、他人が見れば「こぎたない…」としか思えない黒いかさぶたのようなものが、
母体と胎児を結んでいるんですね。
だけどこれを大事にとっとく習慣があるのは日本人だけだとか。
へその緒信仰ですね。
日本人は実質的には意味のなくなった体の一部に象徴的な意味づけをするのが得意。
髪の毛をわら人形に入れて呪詛したり、
抜けた乳歯を屋根やら軒下に放り投げたり、
遺骨をことさらに大事にしたり分骨したり・・・
今回、お父さんがへその緒を切りました。
助産院の先生が「やってみろし」と勧めたこともあって。
直径1cmくらいのソーセージ状のそのホースは、思ったより弾力があって切り離すのに少々力が要ったとのこと。
「ほうずら。これだけ強い絆でお母さんと結ばれてるだよ。」
胎盤も、私は今回初めて見ました。
透き通った薄い膜に包まれた、フリスビーサイズのレバー。
けっこう存在感のある大きさの臓器でした。
グロテスク、といってもいいかも。
「きれいな胎盤だよ」と先生。
そういうことでほめられるのもなんだか奇妙な感覚ですが、うれしい気もしました。
切り取ったへその緒のホースもくっついてます。
これのおかげで、お母さんが食べたものが栄養素となって赤ちゃんに届けられ、
ぎりぎりまで赤ちゃんがおなかにいられ
血液型が違っても大丈夫なようになってるというわけか。
妊娠中最後のほうは重くて圧迫感が気持ち悪くて、同じ哺乳類でも有袋類はいいなぁ、などと愚痴ったものでしたが
これのおかげで、人間は高等生物になれたわけです。
ほとんどの哺乳類はへその緒も胎盤も出産後に親が食べます。
敵に跡を知られないように、処理するという意味もあったりするそうですが、
そもそもとても栄養のあるものだとか。
人間も、へその緒をせんじてのめば病気が治るとかいいますもんね。(日本人だけ?)
また、胎盤を素手で触っていると手がつるつるになるそうです。
コラーゲン効果?!
産院によっては産後の食事に味付けを施して食べさせてくれるところもあるみたいですが、
この助産院ではさすがにそれはありませんでした。
処分するためには医療廃棄物扱いで2500円がかかりますので、先生は一応「どうする?」と聞いてくれましたが、やっぱり食すのも持ち帰るのも遠慮しました。
生で自分のおなかに入ってた臓器が見れただけでも貴重な体験です。
産院でくれた桐の箱に、Kuhのへその緒を入れ、引き出しの奥にしまいました。
10ヶ月間、どうもありがとう。