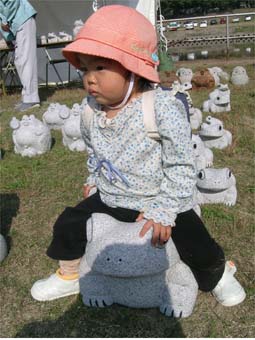サルが出た!
勤務先の事務所のテラスにサル出現!
南アルプス山麓が生息地と言われていますが、甲州街道を渡りいよいよこの高根町にも上がってきたのです。

小さい小猿です。きーきーとかわいらしい声で鳴いていました。
目を合わせたらボス猿が襲い掛かるといわれていましたが、どうも親猿は見当たらず、一匹だけ。迷い猿のようです。
人間を見ても怖がるでもなく様子を伺いながら逆に近づいてこようとします。窓を開けたら入ってきそうな勢いでした。

それにしてもとても寂しそう。
屋根に登って南アルプス方面を見ています。

通りかかった移住者のご主人。
危害を加えるサルでないことがわかるとかわいくなってきて・・・

ついには抱き上げてしまいました。
サルも寒さの奮えが止まり、脱力して体を預けている様子。「ほら、力抜いてるよ。だんだん重くなってきた」
こらこら、孫じゃないんだから。

そのご主人がいったん家に連れ帰ろうとしましたが、さすがに途中で放しました。するとまた事務所に戻ってきて、窓から中を覗き込み、なにやら物欲しげ。かわいいんだけど・・・(困ったナー)

誰か人間から食べ物をもらったのかもしれません。いやに人懐っこいサルでした。事務所にこのまま住みついちゃったりして。